以前に、フラジオについて考えてみたことで、ふと「そういえばバイオリン(ヴィオラ、チェロ、コントラバスも)にはなんでフレットがないんだろうか」という疑問が湧いてきました。
なので今回は、「バイオリンにはなぜフレットがないのか」について調べてみました。
フレットがないのは不便?と思って調べてみた
フレットって何のためにあるの?ギターとの違いから考える
まずフレットとはギターやベースに埋め込まれる形で取り付けられている金属の棒で、音程を視覚的に捉える役割があります。
フレットがあることで、初心者でも最低限どこを押さえれば何の音が出るかわかる、ということですね。
バイオリンにフレットがない理由とは?構造と演奏法からの納得感
そんな重要なフレットがバイオリンにはなぜないのか。
どうやらフレットを埋め込むにはバイオリンが小さく位置調整がとても微妙らしいです。
なるほど、と納得したのと同時に「じゃあなんでチェロとコントラバスにもフレットがないのか」と新たな疑問が生まれました。
それについても調べてみたところ、どうやら弓による演奏方法が関係しているらしいです。
バイオリンのように弓を使用して音を出し続ける楽器は、弾きながら音程を修正したり、ビブラートを併用して細かな音程修正をすることがあります。
その場合フレットがむしろ邪魔になる。
確かにバイオリンってほんの1mm押さえる位置が違うだけで大きく音程が変わるし、弓を引いてる間ずっとその音が鳴り続ける。
そこで音程修正をしようとしたときにフレットがあったら…指が引っかかって音に意図しない波が生まれてしまう。
なるほど確かにフレットがない方がいいような気がしてきました。
フレットがないからこそできる“音の表現”
そしてもうひとつ、フレットがないことで指板に引っ掛かりがなくなりビブラートの表現がより豊かになる利点があるみたいです。
これも確かにフレットがあったら、今のバイオリンの形状ほど響くようなビブラートは表現できないかもしれない。
大昔から存在するものなだけあってなるほど良く考えられてるんですね。
音程がとにかく難しい…でもハマる感覚がすごい!
ただし、フレットがないことで表現は豊かになりますが、やはり身体が覚えるまで音程を取るのがとても難しいというデメリットも間違いなく存在します。
バイオリン系の楽器が初心者に難しいとされている理由が「音程」なんですよね。
他の楽器はここを押さえればその音が出て、最低限メロディーを出すことはできる。
もちろんどんな楽器も楽譜をなぞるだけじゃなく、演奏する、奏でるというレベルに達するまでは練習が必要ですが、バイオリンはまずその音を出す練習から始まります。
そりゃ難しいわけです。
でもバシッと決まった時の気持ちよさは最高です。
少しずつ音程が取れるようになってくると「ハマる」瞬間が来るんです。
もうね、これを味わうと他の楽器に戻れないです。
私は幼稚園~高校卒業までピアノを習っていました。
もちろんピアノの音色も綺麗ですし楽しかったです。
自分が主役(メロディパート)にも脇役(伴奏)にもなれるので、楽しみの幅が広いし音域は楽器一だと思います。
ただ、私はバイオリンの方が自分で音を作ってる感じがしてピアノよりハマってます。
最近は仕事中も早く家に帰ってバイオリン弾きたいなってずっと考えてるくらいです。
スキルアップの勉強も進めなきゃなんですがね…笑
とにかく個人的に弦楽器はいいぞ~ということです!
どんな楽器でも自分が演奏する楽器を一番と思えるのは良いことですね。
大人になってから始めた趣味ではありますがこんなに素晴らしい趣味に出会えたことが本当に幸せです。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
私のバイオリンとの向き合い方や、5年間のリアルな成長記録をまとめた記事も書いています。
練習方法や変化について詳しく綴っているので、もしよければこちらも覗いてみてください。
「独学で始める自信はないけど近くに教室がない」「教室に教室に通う時間がない」そんな人に向けた記事も書いてますので、こちらもよければ覗いてみてください。
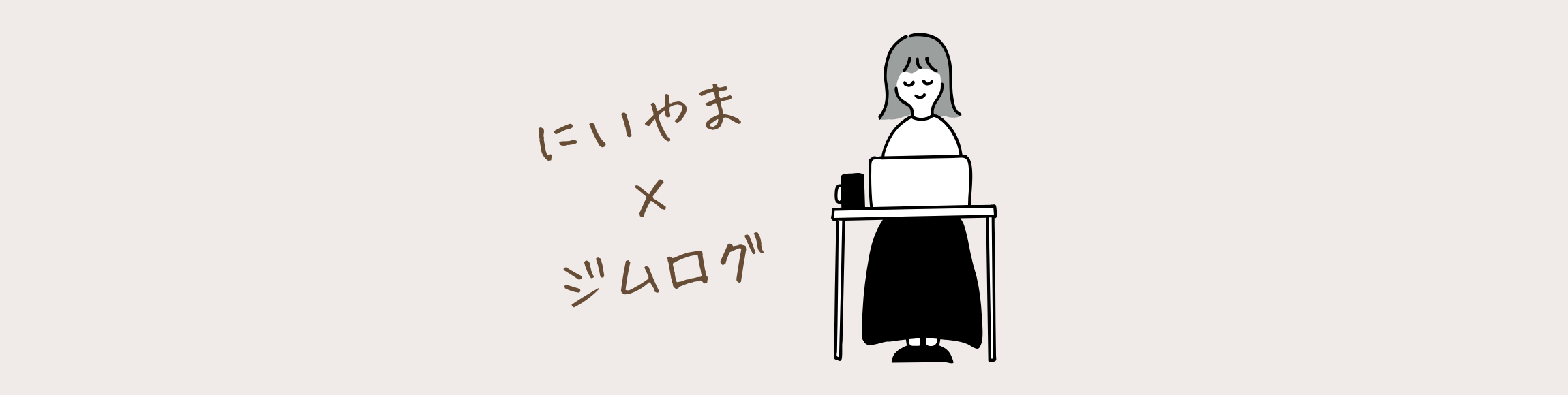
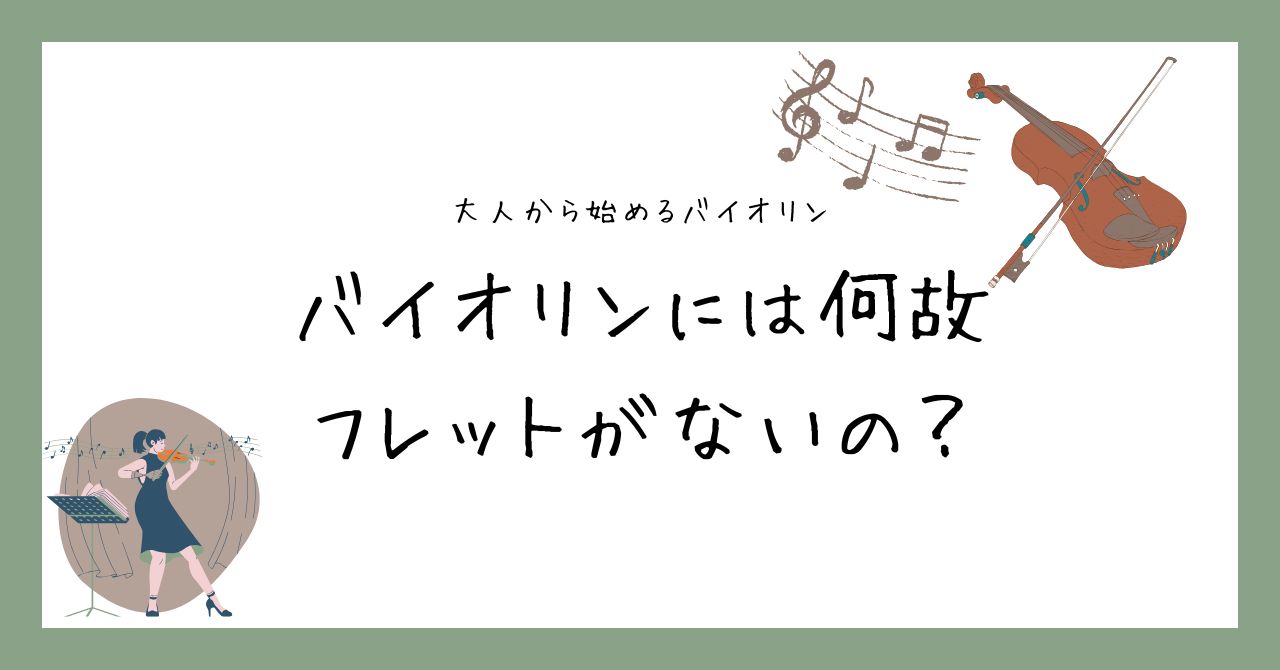
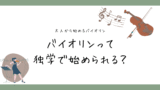



コメント